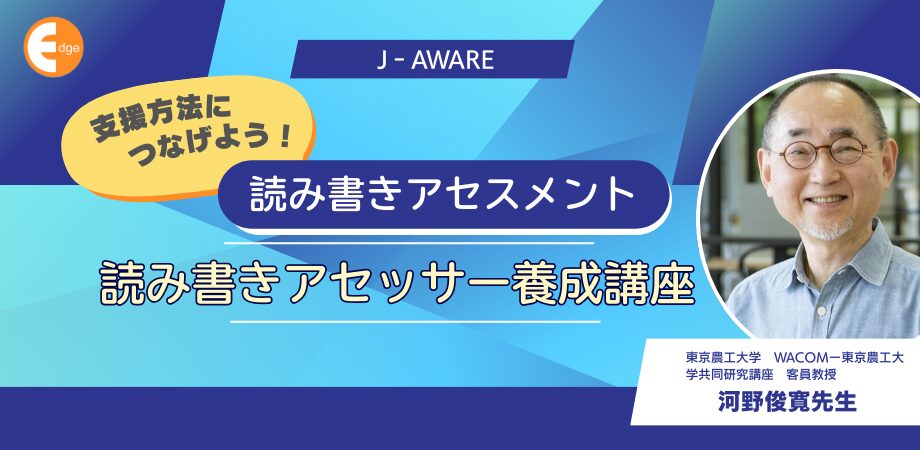こども理解の入門・支援の基礎を学ぶ講座(eラーニング形式)
困りごとの背景を知ることで、関わり方が変わります
発達障害の基礎知識から、ニューロダイバシティ、こどもの心の受け止め方、リフレーミング、こどもの権利やアドボカシー、合理的配慮、身体性からの神経発達症へのアプローチまで、こどもを取り巻く多様な背景に目を向けた講座です。
個々のこどもを理解し、支援に欠かせない視点を体系的に習得できます。
読み書きに困難をみせるこどもへの指導・支援に特化した講座(eラーニング形式)
「読み書きが難しい」背景・理由を理解し、適切な支援方法を学びます
ディスレクシア等の特性理解から、日本語・英語双方での指導、ICT支援の方法等を体系的に習得できます。
現場ですぐに使える支援スキルを身につける講座(eラーニング、オンライン・対面のハイブリット形式)
こどもの困りごとを支える、具体的で実践的な支援方法が身につきます
学校現場はもちろん、放課後等デイサービスや学童クラブ等でも役立つ実践的な支援スキルを学びます。
学習・生活・コミュニケーションの支援等、様々な場面で明日から活かせる関わり方を習得することができます。
支援に繋がる読み書きアセスメント
読み書き困難の原因とアセスメントの方法を学び、結果から「具体的な支援・指導」まで提案できる力を養います。ただ評価するだけでなく、実際に困っている人を助けるための実践的な内容が学べる講座です。
eラーニング講座比較表
支援者養成講座のeラーニング講座一覧表です。 講座の詳細や受講期間等は各ページをご覧ください。
| 講座名 | 発達障害のこどもを理解する講座 こどもにかかわる全ての人のための「こども理解入門」 | 読み書き困難指導・支援講座 こどもの味方の「教え方」 気付いて欲しい読み書きの困難 | J-AWARE 読み書き アセッサー養成講座 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | こども理解の入門、支援の基礎を学ぶ講座 個々のこどもを理解し、支援に欠かせない視点を体系的に習得できる。 | 読み書きに困難をみせるこどもへの指導・支援に特化した講座 「読み書きが難しい」背景・理由を理解し、適切な支援方法を学ぶ | 個別・集団の両方の読み書きアセスメント、支援の提案方法が学べる |
| 受講対象者 | どなたでもご受講頂けます | 読み書きに困難をみせるこどもの 指導・支援をしたい方 | 読み書きに困難があるこどもの支援に携わっている方 |
| 受講条件 | 特になし | 「発達障害のこどもを理解する講座」を受講・修了していると理解がすすみやすい | 支援に携わったことの無い方は
|
| 講座内容 | 発達障害の基礎知識から、ニューロダイバシティ、こどもの心の受け止め方、リフレーミング、こどもの権利やアドボカシー、 合理的配慮、身体性からの神経発達症へのアプローチまで、こどもを取り巻く多様な背景に目を向けた構成。 | ディスレクシア等の特性理解から、日本語・英語双方での指導、ICT支援の方法等を体系的に習得できる。 | 河野俊寛先生による動画形式の講義。読み書きの基礎知識、支援方法、合理的配慮、アセスメント方法。 |
| 学習時間 (目安) | 約10時間 講義視聴時間:9時間30分
修了課題:30分程度 | 約10時間30分 講義視聴時間(日本語):6時間30分
| 約10時間 講義視聴時間:4時間00分
修了課題:1時間程度 |
| 修了条件 |
|
| レポート課題1:提示された検査結果を判定し、どのような提案ができるかを箇条書きで記述する。 レポート課題2:アセスメントを実施しての感想(400字以上) |
| テキスト | 支援者養成講座シリーズ こどもの味方の「かかわり方」 ~こどもにかかわる全ての人のための「こども理解入門」~ (Amazon販売) | 支援者養成講座シリーズ こどもの味方の「教え方」 ~気付いてほしい読み書きの困難~ (Amazon販売) | 子どもの味方の読み書きアセスメント (事務局より郵送) |
| 修了後 | 基礎スキルの強化 フォローアップ「こども理解と支援スキル講座」(年2回) ・参加費(講座修了生) 2,200円(税込) ・参加費(一般) 4,400円(税込) | 専門性の深化 フォローアップ「読み書き支援ラボ」(年2回) ・参加費(講座修了生) 2,200円(税込) ・参加費(一般) 4,400円(税込) 修了生限定コミュニティ「読み書きアップデート」に参加できる | 専門性の高度化 講座修了生は、河野俊寛先生による「演習」に参加できる。 ・演習受講費 11,000円(税込) |
| eラーニング受講料 | 22,000円(税込) | 22,300円(税込) | 33,000円(税込) |
| 各種割引 | 有 ・学割、支援員割・教員割 13,200円(税込) ・学割(25才未満) 8,800円(税込) | 有 ・学割、支援員割・教員割 14,900円(税込) ・学割(25才未満) 9,900円(税込) | 有 ・学割 16,500円(税込) |
| 講座再受講 | 有 3,300円(税込) | 有 3,300円(税込) | 有 11,000円(税込) |
| 割引申請 | 申請方法 『各種講座の受講割引制度について』をお読みください。 | 申請方法 『各種講座の受講割引制度について』をお読みください。 |
|
| 開講期間・回数 | 約4ヶ月/年2回 | 約4ヶ月/年3回 | 約2ヶ月半/年2回 |
| 問い合わせ | 支援者養成講座事務局 発達障害のこどもを理解する講座 hattatsu★npo-edge.jp ※迷惑メール対策のため[★]で表記しています。 ご連絡の際は[★]を[@](半角)に置き換えて送信してください。 受付時間:平日15~18時 (土日・祝日は定休) 担当 : 坂井 | 支援者養成講座事務局 読み書き困難指導・支援講座 edge-yomikaki.support★npo-edge.jp ※迷惑メール対策のため[★]で表記しています。 ご連絡の際は[★]を[@](半角)に置き換えて送信してください。 受付時間:平日15~18時 (土日・祝日は定休) 担当 : 髙尾 | 支援者養成講座事務局 J-AWARE読み書きアセッサー養成講座 shien-assessor★npo-edge.jp ※迷惑メール対策のため[★]で表記しています。 ご連絡の際は[★]を[@](半角)に置き換えて送信してください。 受付時間:平日 (土日・祝日は定休) 担当 : 井上 |
団体でのご受講をお考えの方へ
5名様以上での団体受講に関するご相談を受け付けております。- 教職員研修(教育委員会、小中高等学校、放課後等デイサービス、学童クラブ等の教育・福祉機関)
- 企業研修
- その他、PTA・保護者グループなど、目的や状況に合わせて対応いたします。
団体様向け受講期間の設定、オンラインでの事前相談にもお応えいたします。
団体受講の詳細は →
こちら(PDF)
お問い合わせ
認定NPO法人エッジ 支援者養成講座事務局
団体受講窓口:edge-learning.team★npo-edge.jp
※迷惑メール対策のため[★]で表記しています。
ご連絡の際は[★]を[@](半角)に置き換えて送信してください。
受付時間:平日15~18時(※土日・祝日は定休)
担当:坂井・髙尾